放課後等デイサービス×AI活用のリアル:ChatGPTが”現場スタッフの一人”になった話
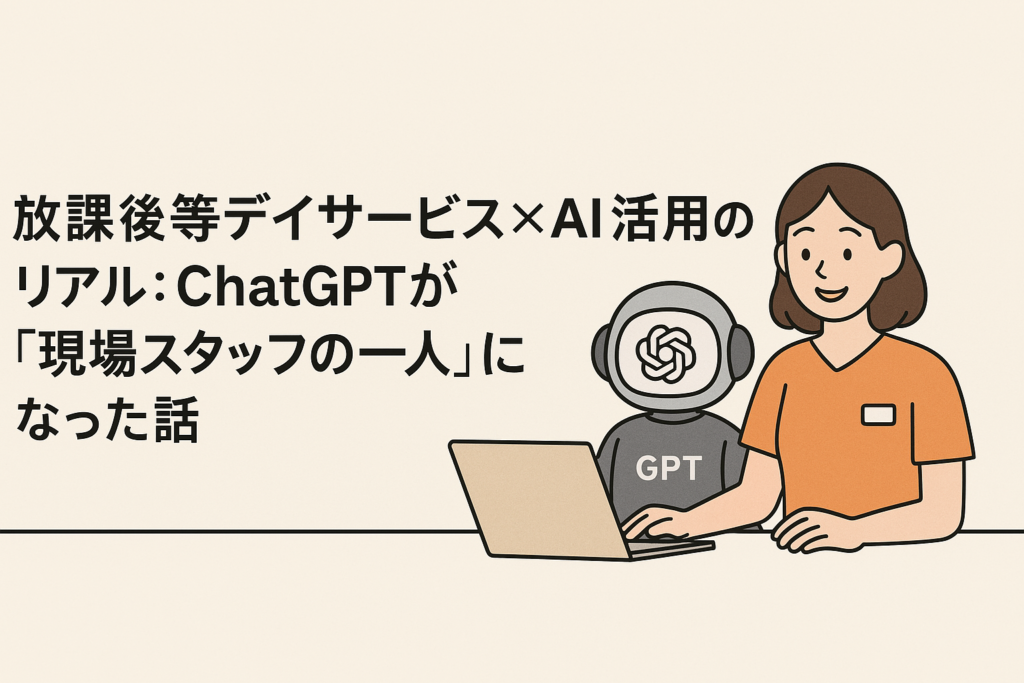
忙しい現場での新たな「仲間」
放課後等デイサービスの日常は、送迎、記録、活動準備、そして何より子どもたち一人ひとりへの支援と、やるべきことが山積み。「もっと子どもとゆっくり向き合いたい」という思いがあっても、時間に追われる毎日です。
そんな中で出会ったのが生成AI「ChatGPT」でした。AIの活用は様々な分野で広がりを見せていますが、「福祉現場での活用は本当に可能なのか?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
今回は私が実際に現場でAIを活用している事例や、その効果と課題、そして今後の展望についてお話しします。
ー
「困ったときの1人目の相談相手」としてのAI
現在、私の放デイでは以下のようにAIを活用しています:
① 保護者向けお知らせ文書の作成
イベントや遠足のお知らせ、月のおたよりなど、保護者への文書作成は意外と時間がかかるもの。「伝える内容」は決まっていても、わかりやすく温かみのある表現にするのは簡単ではありません。
そんなとき、ChatGPTに要点を伝えれば、あっという間に下書きを作成してくれます。「ゼロから書く」ストレスがなくなり、保護者への情報発信がスムーズになりました。
② 活動アイディアの提案
毎日の活動を考えることも、放デイ業務の大きな部分を占めています。天候や子どもたちの状態、学年や人数によって調整が必要で、「今日は何をしよう?」と悩むことも少なくありません。
ChatGPTに「雨の日でも楽しめる、小学生向けの室内遊びを教えて」と尋ねると、様々なアイディアを提案してくれます。中には自分では思いつかないユニークな案もあり、活動の幅が大きく広がります。
③ 支援に関するちょっとした相談
子どもへの対応に迷うことは日常茶飯事。そんなとき、「こんな行動があったとき、どう接したらいいか?」とChatGPTに相談すると、TEACCHやABAなどの理論を踏まえた視点からアドバイスもくれます。
もちろん最終判断は人間の経験と直感によるものですが、「考えるためのきっかけ」としては非常に有効です。一人で抱え込まずに済むことで、心の余裕も生まれます。
④ 細々した業務の効率化
その他にも:
・スピーチの要約
・保護者への返信文の草案作成
・スタッフ間の引き継ぎ文の下書き
・会議での議事録の整理
など、日々の「ちょっとした手間のかかること」をサポートしてくれる存在として、AIは頼もしい存在です。
ー
少しずつ、スタッフにも浸透中
現時点では、全スタッフが日常的にAIを活用しているわけではありません。しかし私は意識的に「きっかけ」を作るよう心がけています。
例えば、1分スピーチの要約をChatGPTに依頼してみたり、「活動案が思いつかないとき、ちょっと聞いてみたら?」と声をかけたり。無理に強制するのではなく、「便利そう」「試してみようかな」と思えるタイミングを作ることで、少しずつ関心が広がっています。
AIは「苦手な部分をそっと補ってくれる存在」として、うまく活用すれば福祉の現場にも馴染んでいくと感じています。
ー
AIと共に働いてみて感じたこと
よかったこと
・とにかく時間短縮になる
・頭の中のモヤモヤが整理される
・「相談できる存在」がいるだけで心が軽くなる
・業務の見える化や言語化がスムーズになる
気をつけていること
・個人情報は入力しない
・出力された内容は必ず自分で確認・修正する
・子どもの個性や関係性はAIには読み取れない
ー
これからの展望
今後は、スタッフ間でのAI活用をさらに広げていきたいと考えています。同時に、子どもたち自身にも「AIって何?どう付き合う?」をテーマに、ちょっとしたワークや対話の時間が持てたら面白いかもしれません。
福祉とテクノロジーは、一見すると距離があるように感じられるかもしれません。しかし実際は、「誰かを支える」「できないを補う」という点で、とても相性の良い分野だと実感しています。
ー
おまけ:よく使うAIへの質問(プロンプト)例
「放課後等デイサービスで、梅雨の時期に楽しめる室内遊びを教えて」
「ヘアカットのお知らせ文を300文字で作って」
「感覚過敏のある子への支援のポイントを簡単に教えて」
「1分スピーチの内容を要約して」
AIは魔法ではありません。 でも、”一人ひとりを支える時間”を少しでも増やすためのツールとして、これからも試行錯誤しながら、現場で活かしていきたいと思っています。
